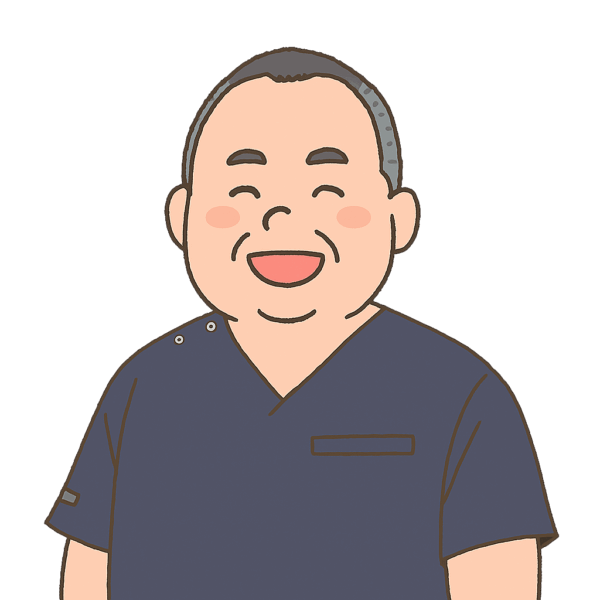- 9月 10, 2025
- 9月 25, 2025
インフルエンザワクチンについて 種類・効果・接種時期について~京都市伏見区醍醐の呼吸器内科が解説~
最初に当院で接種をお考えの方向けに接種期間と費用のお知らせです。
当院では3歳以上の方を対象としております。3歳未満の患者様については小児科などにご相談下さい。
定期接種期間:開始日が自治体により違いますので注意ください
京都市の定期接種開始:令和7年10月15日から令和8年1月31日まで
宇治市の定期接種開始:令和7年10月1日から令和8年1月31日まで
費用
京都市定期接種対象者:75歳以上 1,000円、65~74歳 1,500円
宇治市定期接種対象者:1,500円
それ以外の方:1回3,000円(13歳未満のお子様は2回を推奨しております)
フルミスト(3~19歳):8,000円*フルミストについてはお電話での受付となります
予約開始日
9月29日から受付開始します。Web予約もしくはお電話、受付での予約が可能です。
当院HPはこちら
🚙アクセスはこちら
📅 Web予約はこちら
京都市伏見区醍醐にあります辻医院です。呼吸器内科を中心とした内科クリニックです。
呼吸器といえば、冬場にインフルエンザ感染をきっかけにCOPDや喘息が悪化することが多いです。もちろん心不全などの病気も悪化します。持病をお持ちのご高齢の方はインフルエンザの予防は非常に重要です。
例年10月からインフルエンザの定期接種が開始されます。9月中頃くらいから「インフルエンザの予防接種したほうがいい?」「効果あるの?」「毎年いつごろ打つのがいい?」と質問を受けることが多いです。
毎年お受けするご質問であり、ブログでまとめておこうと思います。
インフルエンザワクチンは“インフルエンザにかからなくなる魔法の薬”ではありません。しかし、発症を抑えたりや重症化を防ぐ効果が科学的に証明されています。
この記事では、一般の方に向けて インフルエンザ予防接種の効果・持続期間・接種のおすすめ時期 をわかりやすく解説します。
インフルエンザとは??
インフルエンザは、インフルエンザAまたはBウイルスによって引き起こされる急性呼吸器疾患です。温帯気候では主として冬季に、毎年、流行(エピデミック)として発生します。
毎年のインフルエンザワクチン接種は、インフルエンザウイルス感染を予防するために大変重要です。ウイルス変異率が高く、新たな変異株が生じ、集団免疫を回避することがあります。その結果、ワクチン株は定期的な更新が必要となります。
ワクチン中身について
抗原選定 — イ体の中に入ってきたときに 「これは自分の体のものではない!」 と免疫が判断して反応する目印のようなものです。
言い換えると、体が異物と認識して免疫反応を起こす“きっかけ”になる物質が抗原です。
インフルエンザウイルスは増えるたびに 少しずつ遺伝子に変化(突然変異) が入り、その結果「抗原」の形も少しずつ変わってしまいます。このため毎年、新しいインフルエンザワクチンが製造されます。日本で製造されるインフルエンザHAワクチン(注射のインフルエンザワクチン)はWHOの推奨株や昨年の抗体反応性や製造効率をもとに国立感染症研究所で検討され、厚生労働省生科学審議会での議論を経て決定されています。
一方で、昨年から登場した経鼻弱毒生ワクチン等の海外で製造され、国内に輸入されるワクチンについては、WHOの推奨株もしくは類似株の中から独自に株の選定を行っています。このため国内製造インフルエンザHAワクチンと株が違っている可能性があります。
4価から3価への切り替え — 2013年に米国で4価インフルエンザワクチン(A/H1N1、A/H3N2、B/ビクトリア、B/山形)が利用可能になりました。しかしB/Yamagata系統のウイルスは2020年3月以降、世界的に検出されておらず、WHOなどの公衆衛生当局は季節性ワクチンからの除外を推奨しました。日本でも今年から3価のワクチンへ切り換えられました。
2025年度インフルエンザHAワクチン製造株
A型株
A/ビクトリア/4897/2022(IVR-238)(H1N1)
A/パース/722/2024(IVR-262)(H3N2)
B型株
B/オーストリア/1359417/2021(BVR-26)(ビクトリア系統)
経鼻弱毒生ワクチン製造株
A型株
A/ノルウェー/31694/2022(H1N1)
A/パース/722/2024(H3N2)
B型株
B/オーストリア/1359417/2021(ビクトリア系統)
誰が打つべきなの??
生後6か月以上のすべての個人に毎年のインフルエンザワクチン接種を推奨されています。
その中でも接種が特に重要とされているのは以下のような方々です。
- 患者さんや感染性材料に曝露する可能性がある医療従事者
- 5歳未満の小児または50歳以上の成人(特に6か月未満の小児)の同居家族/介護者(同居家族には生後6か月以上の子も含む)
- 重症化リスクのある基礎疾患を持つ者の同居家族/介護者(同居家族には生後6か月以上の子を含む)
いつ打てばいい??
成人には毎年、季節性インフルエンザワクチンを1回接種します。
小児では厚生労働省は
インフルエンザHAワクチン
・ 6か月以上3歳未満のものには0.25mLを皮下におよそ2~4週間の間隔をおいて2回注射する
・3歳以上13歳未満のものには0.5mLを皮下におよそ2~4週間の間隔をおいて2回注射する。
・ 13歳以上のものについては、0.5mLを皮下に、1回又はおよそ1~4週間の間隔をおいて2回注射する。
経鼻弱毒生ワクチン
・ 2歳以上19歳未満の者に、0.2mLを1回(各鼻腔内に0.1mLを1噴霧)、鼻腔内に噴霧する。
用法及び用量
とされています。
理想的な接種開始時期は一概に言えません。いつ流行のピークが来るのか予想しにくく、早すぎるとワクチンの効果が低下してしまう可能性が有ります。日本では毎年高齢者の定期接種(自治体が補助を出して行うワクチン接種)が10月からであり、このタイミングに合わせて接種するのがおすすめです。
ワクチンの効果は時間とともに減弱していきます。一般的には接種後2週間程度で効果が出てきて、5か月ほど続くといわれます。過去の研究では、接種後14–41日の群に比べ、42–69日の群はインフルエンザ陽性のオッズ比が1.3倍でした。以後28日ごとに約16%ずつオッズ比が直線的に増加し、154日以上経過群では2.1でした。あまり早すぎると、効果がなくなりインフルエンザ流行期後半でインフルエンザにかかってしまう可能性がでてきます。
副作用について
アレルギー
- インフルエンザワクチンでアナフィラキシー歴:これは禁忌(打ってはいけない)になります。
- 卵アレルギー:禁忌ではないとされています。接種前に卵アレルギーの有無を確認する必要も不要とされています。インフルエンザHAワクチンは微量の卵蛋白を含みますが、摂取でアナフィラキシー歴がある患者でも反応を誘発するほどではないとされています。
ギラン・バレー症候群(GBS):手足のしびれや麻痺、筋力の低下などが見られます。接種後すぐに出ることもあれば数週間経ってから見られる場合もありますが、ワクチン接種後2週目がピークで、6週間以内の発症がほとんどです。
頻度はかなり低く100万人に数人といわれます。インフルエンザの重症化リスクがある個人では、ワクチン関連GBSのわずかなリスクよりもワクチン接種による重症化予防の利益が上回る可能性が高いとされています。さらに、インフルエンザ感染自体が引き金となるギランバレー症候群のリスクを、ワクチンが低減するとされており、基本的にはギランバレー症候群を心配して接種を行わないということは推奨されません。
その他の軽微なもの
- 局所反応:最も一般的なものになります。注射部位の疼痛が2日程度でます。軽度発熱、筋痛、頭痛、倦怠感は稀で1–2日で軽快するとされています。
経鼻弱毒生ワクチン:鼻漏・鼻閉・頭痛・咽頭痛が多いとされています。生ワクチンのため、10%程度の人に軽いインフルエンザ様の感冒症状が出るとされます。咳嗽、鼻汁が出ることが多く、軽い鼻づまりやのどの違和感は30〜40%に見られます。、また一部の人に発熱、筋肉痛などの軽いインフルエンザ様症状を認めますが、注射ではないので接種部位を腫らすことはないです。そのときに検査をすると弱毒生ワクチンのため、インフルエンザ陽性になることがあります。
インフルエンザワクチンは効果あるの??
厚生労働省のHPから引用いたします。
国内の研究によれば、65歳以上の高齢者福祉施設に入所している高齢者については34~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止する効果があったとされています※1。
6歳未満の小児を対象とした2015/16シーズンの研究では、発病防止に対するインフルエンザワクチンの有効率は60%と報告されています※2
現行のインフルエンザワクチンは、接種すればインフルエンザに絶対にかからない、というものではありません。しかし、インフルエンザの発病を予防することや、発病後の重症化や死亡を予防することに関しては、一定の効果があるとされています。
※1 平成11年度 厚生労働科学研究費補助金 新興・再興感染症研究事業「インフルエンザワクチンの効果に関する研究(主任研究者:神谷齊(国立療養所三重病院))」
※2 平成28年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金(新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業「ワクチンの有効性・安全性評価とVPD(vaccine preventable diseases)対策への適用に関する分析疫学研究(研究代表者:廣田良夫(保健医療経営大学))」
当院でも10月からインフルエンザワクチンの接種を開始予定です。
今年からフルミストの接種も開始いたします。
フルミストについては、当院では2歳以上から19歳未満(18歳11ヶ月まで)の方を対象とさせていただきます。
- 妊娠中あるいは妊娠の可能性がある女性。
- 治療のためにサリチル酸系医薬品:アスピリン、サリチル酸ナトリウム等、ジクロフェナクナトリウム、メフェナム酸を服用している人。
- 5歳未満で喘息の治療を行っている人、または、1年以内に喘息の発作があった人。
- 心疾患、肺疾患、肝疾患、糖尿病などの代謝性疾患、血液疾患、神経系疾患、免疫機能低下などの慢性疾患を持っている人。
- 医療従事者で、重症者治療ユニットや悪性腫瘍治療ユニットで働いている人。
- 免疫機能が低下した人と日常的に接する、介護者や家族など。
- インフルエンザワクチン接種後にギランバレー症候群を発症した経験がある人。
は接種ができません。海外では49歳までは使用可能なため、上記のような注意喚起がなされています。アスピリン、サリチル酸ナトリウム等、ジクロフェナクナトリウム、メフェナム酸を服用している方はライ症候群やインフルエンザ脳炎・脳症の重症化との関連性を示す報告があるためです。2歳から19歳未満で当てはまる方は少ないかもしれませんがご注意下さい。
費用
京都市定期接種対象者:75歳以上 1,000円、65~74歳 1,500円
宇治市定期接種対象者:1,500円
それ以外の方:1回3,000円(13歳未満のお子様は2回を推奨しております)
フルミスト(3~19歳):8,000円*フルミストについてはお電話での受付となります
インフルエンザワクチンの予約についてはこちらから *9月29日から予約開始
定期接種開始日
ようやく京都市の定期接種開始日の連絡が参りました。
京都市の定期接種開始:令和7年10月15日から令和8年1月31日まで
宇治市の定期接種開始:令和7年10月1日から令和8年1月31日まで
当院では3歳以上の方を対象としております。3歳未満の患者様については小児科などにご相談下さい。
当院HPはこちら
🚙アクセスはこちら
📅 Web予約はこちら